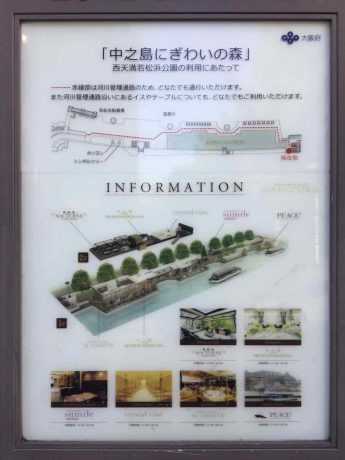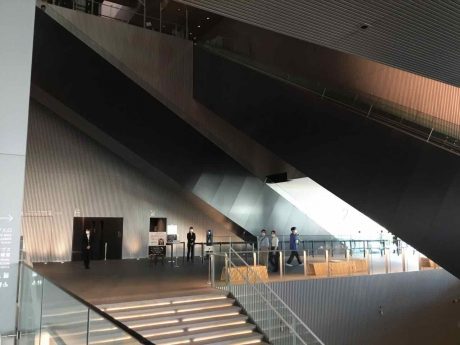令和4年も残り少なくなりました。
今年はどんな一年だったでしょうか?
世界な出来事も多い中、建築関係もコロナ禍の混乱によるウッドショックや
戦争による資源高で工事費にも大きな影響が続いています。
3月に竣工した大神の家2も木材価格高騰の影響でコスト調整に苦労しました。
現在、設計中の宇部の家のリノベーションも減額調整などで年を越します。
それでも、コストを抑えるために「安かろう悪かろう」では後々問題が起こります。
限られた費用の中でも何が一番大切なのかをしっかり吟味し
割り切るところは潔く割り切ることを上手にできれば
タイトなコストでも愛着のわく建築を生み出すことは可能です。
大神の家2も幾つかの要望を割愛しなければいけませんでしたが
「家族がのびのびとおおらかに暮らす」というテーマはぶれることなく実現。
家がまるで公園や広場のように、居心地よく過ごせる空間にこだわりました。
周南のまちでも、「車から人へ」の動きが少し垣間見られました。
11月に行われた社会実験では、御幸通りが公園のような豊かな場に。
コロナ禍でも人々がゆったりと交流できる場の大切さが再認識されました。
様々な不安の多い現代だからこそ、人と人が孤立するのではなく、
家でもまちでも人と人がつながって穏やかに過ごせる場が大切だと思います。
TIMEはそんな場や時間の大切さによりフォーカスして
その価値を提供することにこだわっていきたいと思います。
2022.12.28 設計事務所 TIME