
心静かに庭に向かう
禅林寺(永観堂)、釈迦堂の深い縁側と前庭、
とても静かな時間が流れています。
右手には勅使を迎える唐門と前庭にある盛砂が定位しています。
盛砂は勅使が身を清めるためのものだそうです。
縁側には目の覚めるような鮮やかな五色幕がかかっており
深い縁側空間をその陰影と風の動きによって濃度を上げています。
静かなのに濃密なこの空間、なかなか鋭いです。
2017.5.17 設計事務所 TIME

2017.5.17 設計事務所 TIME


2017.5.16 設計事務所 TIME



2017.5.12 設計事務所 TIME



2017.5.11 設計事務所 TIME






2017.5.9 設計事務所 TIME







2017.5.2 設計事務所 TIME









2017.4.28 設計事務所 TIME
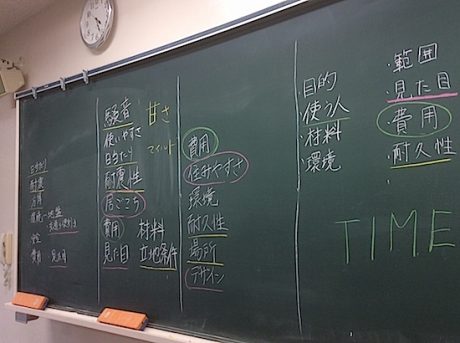
2017.4.27 設計事務所 TIME

2017.4.25 設計事務所 TIME
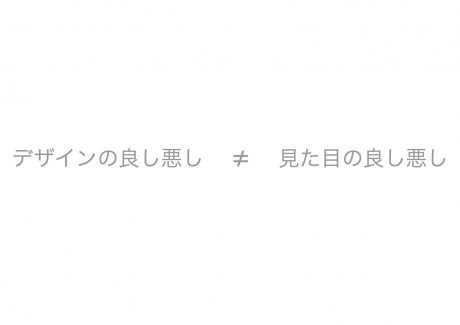
2017.4.19 設計事務所 TIME