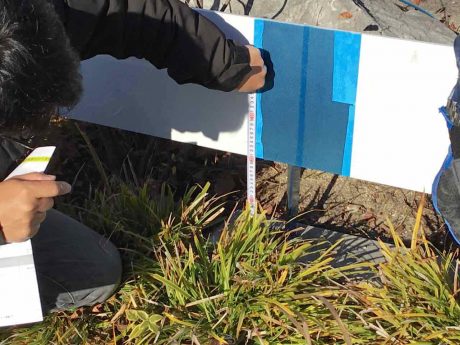今年は臼杵の仕事で1年間、現場に通いました。
昨年の11月に始まった工事は着工からほぼ1年がかりでようやく完成、
標準的な住宅の2倍以上の時間を要しました。
建主も工務店もその時間にとても寛容であったことが功を奏し
「早いほうがいい」というのが当たり前の世の中で
あえて時間をかけることの共通意識を持てる仕事でした。
話は変わりますが
今から28年前、1年2ヶ月をかけて世界を旅しました。
当時、東京の設計事務所で働いていましたが
時代はバブル全盛期で、次から次に仕事が舞い込み、
処理するだけで精一杯、とにかく時間に追われていました。
そもそも建築をじっくりと考えて設計したいと思って選んだ設計事務所でしたが、
バブルの勢いで、考える余裕すらなくなっていました。
そこで一念発起、
一旦仕事を辞めて、世界の建築を自分の目で見て回ろうと思ったのです。
猫の手も足りたい状況の中でしたが、所長に無理を承知でお願いし、
抱えていたプロジェクトを1年かけて終わらせると、
いよいよ旅をスタートさせたのです。
旅のルートはロシアをシベリア鉄道で横断し、東ヨーロッパを南下してエジプトへ。
その後、中東を回ってヨーロッパ、最後にアメリカを巡るというものでした。
世界の建築を巡るにあたり、古代から現代に至る建築の数々の資料を整え
建築に関する情報は万全でした。
ところが、もともと海外旅行の経験は多くなかったこともあり
旅先の事情や現地での対応力を身につけていなかったため
最初からトラブル続きでした。
シベリア鉄道ではこそ泥に金をすられ
モスクワでは風邪をひき込み、エジプトでは腹を下すなど
最初の1ヶ月で心身ともにかなりのダメージを受けてしまいました。
その間、とにかく遅れを取り戻そうと焦れば焦るほど体調が乱れて、
建築を見る集中力も続かないという悪循環でした。
その後、中東のシリアで出会った日本人旅行者とトルコで再会し
しばらく一緒に旅をする事になりました。
彼は日本を出てすでに3年以上経っており
中東の前はアフリカ大陸を縦断して南アフリカの喜望峰まで至り
1年8ヶ月をかけてここまで来たとの話でした。
途中、病気で入院したり、強盗に襲われたり
荷物を丸ごと盗まれたりと、なかなかタフな経験をしていました。
それでも出会ったときには、ちゃんとリュックに必要な旅行道具がそろっており
なんともたくましさを感じました。
その彼とはトルコを2週間ほど一緒に旅しましたが
私とは時間の使い方がまるで違う事がとても興味深かったのです。
まちや遺跡など、様々なものを見て回りましたが
出歩くのはせいぜい数時間から半日ほど、
あとはホテルかカフェでのんびり過ごすのです。
それまで、中東各国ではバスの時間を緻密に調べて
一分でも一秒でも無駄にしないように時間を使おうとしていました。
まるで東京で暮らしていたときのような時間の使い方は
中東という場所ではうまくいかず、ストレスばかりがたまっていました。
せっかく自由な時間ができたのに、自分は何をしているのだろう?
トルコを旅するうちに、そのことに気づきました。
それまでは、とにかく自分が動き回って何かを得ようとしていましたが
トルコでは、自分は動かずに周りの動きを感じることができることを発見したのです。
やみくもに何かを得ようと焦っても、大した成果は得られない。
むしろ、じっくりと時間をかけることで見えてくることがある。
その後に訪れたモロッコでのエピソードですが
サハラ砂漠の入口にあたるワルザザードというまちがあります。
そのまちで長距離バスを待っていたところ、9時過ぎに来るはずのバスが一向に現れません。
バスを待っている人はいるのですが、誰も時間を気にするそぶりがありません。
近くにいたモロッコ人にバスはいつ来るんだろうと何気に聞いてみると
彼は一言、「インシャッラー」と答えました。
つまり、そんなこと、神様次第だよ、と言う意味です。
なるほど、そこは広大なアフリカ大陸、
細かいことを気にしていても仕方がないではないか。
妙な説得力を感じたものです。
この旅は、世界の多くの建築に触れることができただけでなく
本質的な「時間の価値」のようなものに気づかせてくれた貴重な経験でした。
現代社会に生きる私たちは、日々時間に追われがちです。
少しでも早く、早くと気が急いて
気づくと目的だったはずのものはあっという間に過ぎ去っていたりします。
いまだに続いているコロナ禍もあと数年続くという専門家もいます。
1日でも早く日常が戻りますようにと願うのは人情ですが
願ってもかなわないことも、この世には存在します。
そんなとき、逆に、今起こっている現象を俯瞰してみることで
この状況でもストレスを減らし、豊かさを見つけることもできると思えるのです。
時間は誰にでも平等であるはずですが
使い方によっては、人それぞれに生まれる時間の価値が変わってきます。
私にとっては、世界旅行で得た時間の使い方が
いまの日本でも十分に生かせるものだと思っています。
仕事では常に締切りや期限を求められるのは仕方のないことですが
それでも、できるかぎりじっくりとかみしめて時間をかけるよう意識しています。
建築をデザインし、つくることでもその大切さは同様で
それはその先の「豊かなくらし」につながっていくと信じています。
話がかなり長くなりましたが
TIMEはその「豊かなくらし」や「豊かな日常」をサポートすべく
来年もポジティブに時間をかけて、その価値を提供していきたいと思います。